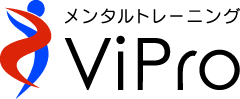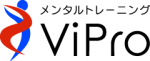メンタルトレーナーの宇井野です。

「スランプ」とは。
プロスポーツの世界だけでなく、クラブ活動などでも、日常的に「スランプ」という言葉を使うようになりました。
みなさんも経験があるかもしれませんが、「スランプ」になると気持ちが沈んで、出口のないトンネルに入り込んでしまったような不安感にとらわれます。
また、「スランプ」を脱しようともがけばもがくほど、状況が悪くなるように感じることがあります。
そして選手の多くは、「スランプ」を「練習量アップ」によって克服しようとします。
多くの時間をかけることで「スランプ」脱出が実現できることは実際にありますが、克服できなかったときには、無力感や悪いイメージをより大きくする結果になります。
そもそも「スランプ」は、よいフォームにズレが生じ、それが反復されることによって、間違ったフォームの神経回路が強化された結果起こります。
そして、強化された悪いフォームのイメージが、脳で正常なフォームだと勘違いされることで、本格化していきます。
人間の体の反応はイメージに則って示されるのでよいイメージよりも悪いイメージのほうが強化されていれば、結局は悪いイメージどおりに体を動かしていることになるのです。
したがって、「スランプ」のときは、その悪いイメージを払拭することがポイントになります。
「スランプ」の初期段階であれば、問題のプレイ(スキル)から離れるだけで、自然によいイメージに戻るものですが、その段階ではたいていの選手は「今日は調子が悪かったな」程度にしか思っておらず、ズレがイメージとして残っているうちに次の練習をしてしまいます。
すると、ズレたフォームのイメージが強化されていくことになります。また、「スランプ」の初期段階では、体の一部の動きだけがズレているにもかかわらず、「ああでもない、こうでもない」と体全体の動きを修正しようとします。
そうなると、よい動きをしていた他の部分にまでズレが生じて、体全体の動きがおかしくなり、結果的に「スランプ」をいっそう深刻なものにしてしまうこともあります。
このように、よいイメージのうえに新しいイメージが上塗りされていくと、脳が混乱状態に陥り、その混乱が不安を呼ぶことになります。
そして、その不安がさらに脳を混乱させてしまうという悪循環に陥っていきます。
「スランプ」の長期化は、「スランプ」を技術面だけから修正しようとした結果起こるものといえるので、その克服は心身両面から考える必要があります。

「スランプ」の原因。
「スランプ」の原因はいくつか考えられますが、主なものとしてフォームの乱れや一連の動作におけるズレがあげられます。
私たちはプレーしているとき、それぞれの動きについて自分なりの感覚をもっています。
調子のよいときは、正しい動きのイメージに対して、それに対応する感覚をもっています。
ところが、自分では正しいイメージどおりに体を動かしているつもりでも、間違った体の使い方をしていることがあります。
このとき、自分なりの感覚にもズレが生じていることになります。
自分ではいつもと同じく正しいイメージどおりのプレーをしているつもりなのに全然結果がでないということになれば、「一体なぜなのだ」とますます深みにはまってしまいます。
そんなときは、「スランプ」に陥っている現在の動きと、好調時の動きをチェックする必要があります。
VTRを使って一連の動作を比較し、異なっている部分を探し出してズレを修正しますが、同じ動きを比べるわけですから、ひじが少し下がっていた、足の上げ方が足りなかったなど、いろいろな点に気づくと思います。
このとき大切なことは、実際の動きを修正するのはもちろん、「動きに関する感覚」についても修正するということです。
正しい体の使い方ができていなかったにもかかわらず、イメージどおり動いていると思っていたところに原因があるわけですから、感覚そのものにもズレが生じていたことになります。
この修正が早い段階で実行できれば、それほど重症にはならないでしょう。
なぜなら、この段階では、正しいプレーのイメージが頭の中に残っているので、修正しやすいからです。
ここで覚えておきたいのは、動きのズレが体の一部だけのものであるなら、その部分だけに焦点を当てて、イメージの中で繰り返しそのズレを修正するということです。
悪いイメージの原因である一部分だけを徹底的にイメージの中で修正できれば、それ以外はもともと正しいイメージなわけですから、両者のイメージを合体して正しいイメージにすることができます。
「スランプ」のときは、焦りからつい体全体の動きをいじりたくなるものですが、それがかえって実際の動きや、動きのイメージを混乱させることにつながるのです。

「スランプ」の原因がわかっていれば次にやることも見えてきます。
そのためにも日頃から好調時とそうでない時の映像を撮っておくことをおすすめいたします。
やり投げ北口選手の例。
さいごに、先日某番組にて女子やり投げの日本代表である北口選手のトレーニングなどが放送されていました。
その中で不調(スランプ)についても触れられていましたので少しご紹介したいと思います。
北口選手は自分自身の中でパフォーマンスがなかなか上がってこないことに悩んでいました。
五輪前の国際大会で優勝した際もなぜ優勝できたのかわからない、手応えがないような状態だと話していたのが印象的でした。
このままでは五輪で戦えない。
そんな中で不調の原因を探るべく大学の教授などに依頼をして姿勢に問題があるとの指摘を受け姿勢を正すための特殊な椅子に座って日常を過ごしたりしていました。
また最も印象的だったのが、肩や肘、膝の検査を受け異常がないことを医師から伝えられた後のインタビューでの言葉でした。
「自分の体の中に異常がないとわかると気持ち的にも楽になる。」
モヤモヤしたまま練習を続け、自分でも気づかないうちに体が痛みその影響でフォームなどを崩してパフォーマンスが下がっていることも考えられます。
身体的にも精神的にも早めに対処することが大切であることがわかったと思います。
また、日頃からの体のケアをすることで結果的に北口選手のように心のケアもしていることがよくわかったのではないかと思います。
心と体は密接に関係しています。
みなさんもぜひ参考にしていただければと思います。