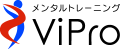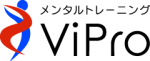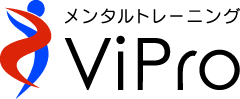メンタルトレーナーの宇井野です。
あなたは緊張する本番前、こう思うタイプでしょうか?
- 「なんとかなるさ!」と笑顔で前に進む
- それとも「最悪を想定して、準備を完璧にしよう」と慎重に考える
どちらが良いのか、気になりますよね。
今回は、こうした「思考パターン」についてスポーツ心理の視点からお話しします。
■ 二つの思考パターン:「楽観主義」と「防衛的悲観主義」
明るい未来を信じて行動するタイプを「楽観主義」と呼びます。
一方、最悪の状況を想定して対策を練るタイプは「防衛的悲観主義」と呼ばれます。
結論から言えば、どちらの思考パターンでも実力を発揮することは可能です。
大切なのは、「自分の思考傾向を理解して、それに合った準備や行動をすること」。
実際、日本人選手には防衛的悲観主義の傾向が強いといわれています。
■ 金メダリスト・大野将平選手の思考法
東京オリンピックで金メダルを獲得した柔道の大野将平選手も、防衛的悲観主義の代表例です。
彼は自分についてこう語っています。
「自分をどうしたら倒せるのか、自分自身がどうしたら負けるのかを考える」
このように、大野選手は“悲観的に考える”自分を無理に変えようとはせず、受け入れたうえで準備と対策を徹底しました。
柔道全日本男子チームの前監督・井上康生氏も、「負けることを想定し、課題を一つひとつ潰していく」という思考を大野選手に伝えています。
■ あなたはどちらのタイプ?簡単な見分け方
- 楽観主義の人:
成功のイメージを描くと、不安が軽くなる。 - 防衛的悲観主義の人:
失敗のイメージを描いておくと、不安が減る。
どちらが自分にとって安心できるかが、見分けるポイントです。
ちなみに、思考パターンは固定されたものではありません。
体調やメンタルの状態、年齢、環境などによって変化します。
スポーツでは楽観的でも、仕事では悲観的という人も多くいます。
大切なのは「バランス」と「自己理解」です。
■ 防衛的悲観主義は“生き残るための能力”だった?
そもそも私たち人間は、脳の構造上「ネガティブなこと」に注意が向きやすくなっています。
なぜなら、人類がサバンナで暮らしていた時代、
危険(=ネガティブな事象)を察知できた者だけが生き残ることができたからです。
例えば──
木の上に熟したバナナがなっていても、近くにライオンがいたらどうしますか?
当然、バナナより命の危険を優先して逃げますよね。
このように、ネガティブな感情は「私たちの命を守ってくれたシステム」でもあるのです。
■ ネガティブな感情とうまく付き合う
たとえばある日、20回もいいことがあって、1回だけ嫌なことがあったとします。
それでも、多くの人は「うまくいかなかった1回」に意識が向いてしまうものです。
- 「もっと別のやり方があったのでは?」
- 「なぜあんな失敗をしてしまったんだろう」
こう考えることは、ある意味で自然な反応です。
むしろ、それを分析することで成長につながることもあります。
ただし、「いつまでも引きずる」「クヨクヨが止まらない」という状態が続くのなら、ちょっとした見直しが必要かもしれません。
■ まとめ:思考傾向は“知ること”から始まる
私たちは、良いことを過小評価し、悪いことを過大評価しがちです。
でも、そうしたネガティブな傾向こそが人間の「正常な反応」であり、「備わった能力」なのです。
自分を責めすぎる必要はありません。
もし不安でいっぱいになったときは、ぜひこの話を思い出してください。
落ち込むのも、悪いイメージをしてしまうのも、人間として当然のことです。
それは決して悪いことではありません。
そして、自分がどの思考タイプに近いのかを知ることで、
不安と向き合いながら、自分に合ったプランや準備を立てることができるようになります。
あなたの思考パターンに合ったメンタルの使い方を見つけてみてください。
それが、きっとあなたらしい成果につながるはずです。